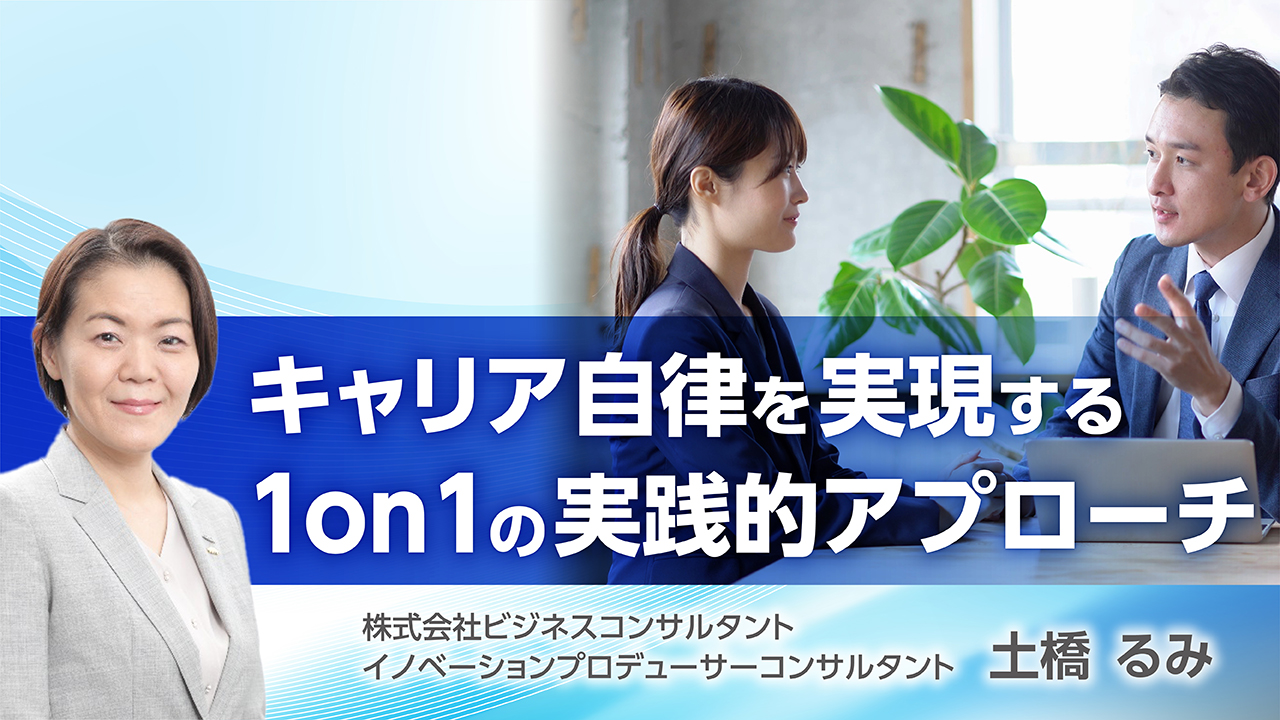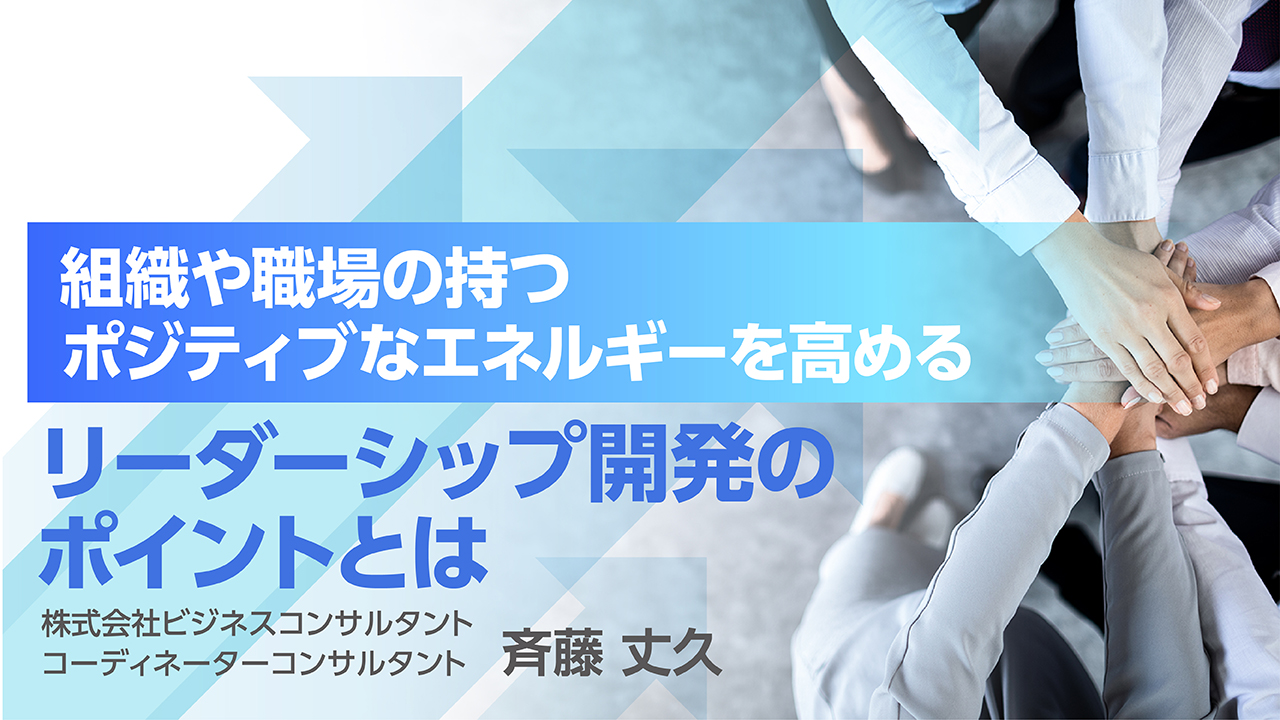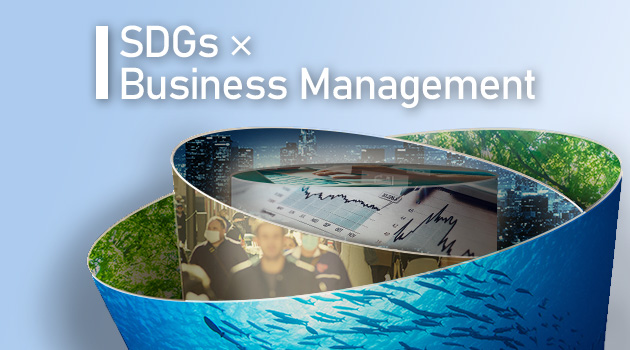若手育成の効果的な方法とは?最新調査から見える課題と解決策を紹介
「若手社員の育て方を変える必要がありそうだが、具体的にどうすればよいかわからない」「任せられる仕事が増え、これから活躍を期待したいというときに辞めてしまう」そんな悩みを抱える人事担当者や管理職は少なくありません。
明確な問題が表面化しているわけではないものの、若手の育成や定着に不安を感じ、早めに若手社員に対して手を打ちたいと考える組織が増えています。
本コラムでは、若手社員の育成における悩み、最新の傾向と課題、そして若手育成のポイントと具体的な方法についてご紹介します。