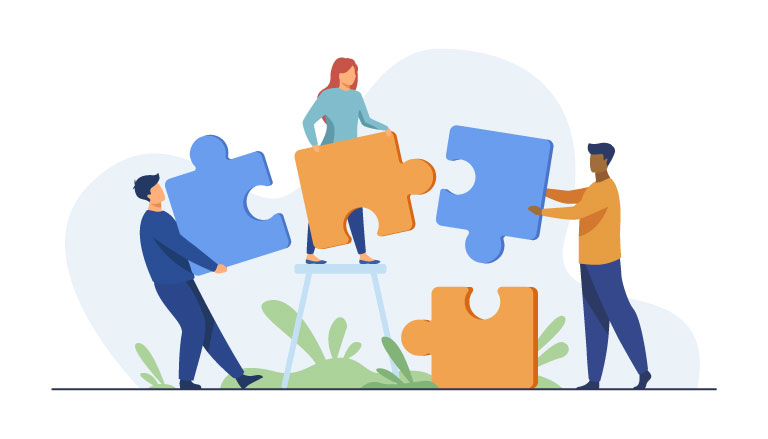新人研修に役立つ!目的別に選べるグループワークのネタ20選をご紹介
- 新入社員研修で活用できるグループワークは、プレゼンテーション型、ビジネス型、作業型、ゲーム型の4つの形式があり、それぞれ目的・効果に違いがあります
- 学びを深めるためには、研修の目的に沿ったグループワークを選び、ワーク後の振り返りをていねいに行いましょう
プレゼンテーション型のグループワークのネタ

プレゼンテーション型は、与えられたテーマについてチームで話し合い、最終的に発表を行う形式のグループワークです。この形式では、情報を収集・整理する力、論理的に考える力、そして相手にわかりやすく伝える力など、社会人として欠かせない伝える力が養われます。加えて、求められる成果物を正確に把握する力や、役割分担・時間管理など、業務遂行に必要な多様なスキルも育むことができます。
特に新入社員にとっては、チームで協力しながら1つのアウトプットを作り上げる過程が、主体性やコミュニケーション力の向上につながります。発表という明確なゴールがあることで、自然と議論が活性化し、目的意識や責任感が芽生えるのも大きなポイントです。
さらに、他チームの発表を聞くことで、自分たちにはなかった視点や考え方を学ぶ機会にもなり、視野を広げることができます。
ここでは、新入社員研修に適したプレゼンテーション型グループワークの具体的なネタを5つご紹介します。
会社案内を作成し、発表する
目的:企業理解の深化、伝える力の習得
グループごとに自社の会社案内を作成し、全体の前で発表します。ホームページや研修期間で得た社内資料を基に、自社の理念やビジョン、歴史、価値観、組織構造、事業内容、強みなどを整理し、”初めて会社を知る人”向けにわかりやすい会社案内を作成します。模造紙やスライドを使って発表することで、情報を取捨選択する力や、視覚的に伝える工夫も求められます。
会社の理解を深めるだけでなく、どう伝えれば相手に魅力が伝わるかを考える良い訓練になります。
社会人として大切だと思う行動を議論し、事例付きで発表する
目的:ビジネスマナーの理解、実践力の向上
グループごとに「社会人として求められる行動」についてディスカッションを行い、その内容を具体的な事例とともに発表します。発表は、実際の職場を想定したロールプレイ形式で行うと、具体的な行動としてイメージができるようになり、より効果的です。
■テーマ例
・報連相(報告・連絡・相談)の重要性
・時間厳守の意識
・適切な敬語や言葉遣い
ビジネスに関するテーマについて議論し、発表する
目的:ビジネス視点の醸成、未来志向の思考力育成
ビジネスの未来をテーマに議論します。新入社員ならではのフレッシュな視点で考えることで、柔軟な発想や課題発見力、論理的思考力が養われます。調査力や情報収集力も求められるため、ビジネスパーソンとしての基礎力や論理的にわかりやすく伝える力も育むことができます。
■テーマ例
・自社の業界は10年後、どのように変化しているか?
・人工知能(AI)やDXの進展が自社のビジネスに与える影響とは?
・今後、企業が生き残るために必要な価値提供とは?
社会問題に関するテーマの解決方法を議論し、発表する
目的:課題解決力の強化、社会的視野の拡大
身近な社会課題をテーマに設定し、その背景や現状を踏まえたうえで、解決策をチームで議論・発表します。企業の社会的責任(CSR)や持続可能性について考えるきっかけになり、社会的視野の拡大にもつながります。
■テーマ例
・当社が貢献できるSDGsのゴールとは?
・カーボンニュートラルに向けた自社の取り組みは?
・地域活性化と企業の関わり方はどうあるべきか?
日常的なテーマについて議論し、発表する
目的:発想力・コミュニケーション力の向上、リラックスした雰囲気づくり
身近で取り組みやすいテーマを通じて、柔軟な発想や対話の練習を行います。
ビジネスに直接結びつかない題材であっても、自己表現や相互理解を促すことで、研修の場に安心感と一体感を生み出すことができます。特に研修初期のアイスブレークや、プレゼンテーションへの苦手意識を払しょくしたい場面で効果的です。
■テーマ例
・理想の働き方とは?
・効率的な朝の過ごし方
・職場で好印象を与える言動とは?
このように、プレゼンテーション型のグループワークは、テーマの設定次第で企業理解やビジネスマインド、課題解決力など、さまざまな力をバランスよく伸ばすことが可能です。研修の目的に応じて、適切なワークを選定することをおすすめします。
ビジネス型のグループワークのネタ

ビジネス型は、実際の業務やビジネスシーンを模したグループワークを通じて、社会人として必要な「仕事の進め方」を体験的に学ぶ形式です。段取り力、報連相、役割分担、時間管理、ビジネスマナーなど、働くうえでの基本行動を習得することが目的です。
頭で理解するだけではなく、実際に手と体を動かすことで、仕事の流れやチームで働く感覚をつかむことができます。そのため、配属後の「思っていたのと違う」というギャップを減らす効果があります。
ここでは、実践的で効果の高いビジネス型グループワークのネタを5つご紹介します。
来客対応ロールプレーイング
目的:ビジネスマナーの習得、臨機応変な対応力の強化
5~8名のグループに分かれ、営業役、受付役、お客さま役などの役割を決め、提示されたシチュエーションに沿ってロールプレーイングを行います。名刺交換、席への案内、あいさつ、商談の入り方など、来客対応における一連の流れを実践形式で学びます。
想定外の質問やアクシデントにも対応する場面を盛り込むことで、マニュアルに頼らない柔軟な対応力も鍛えられます。終了後は、良かった点・改善点をフィードバックします。
制限時間内で業務指示書をもとに作業計画を立てる
目的:段取り力、時間管理力、チームワークの向上
仮想の業務指示書(例:イベント準備、資料作成依頼など)をもとに、誰が・いつまでに・何をするか?をチームで計画立てするワークです。限られた時間のなかで、優先順位を考えながら効率的なスケジュールを組むことが求められます。
役割分担やリスク管理も意識させることで、実務に直結する段取り力やチーム内のコミュニケーション力が鍛えられます。
顧客対応のフローチャートを作成する
目的:業務整理力、課題発見力の向上
クレーム対応、商品説明、問い合わせ対応など、想定される顧客対応フローをチームで整理し、フローチャートとして可視化します。
業務を分解して整理することで、どこにリスクが潜んでいるか、どのタイミングで報連相が必要かを考える力が養われます。実際の業務の流れを理解しやすくなるだけでなく、問題発見・改善意識も高まります。
上司への報告メールをグループで作成し、評価し合う
目的:ビジネス文書力、簡潔に伝える力の習得
上司に業務報告をする、というシチュエーションでメール文をグループで作成します。報告内容の整理、要点を押さえた文章構成、ビジネスメールのマナーなどを意識しながら取り組みます。
完成後は、チーム同士でメール文を交換し、読みやすいか、必要な情報が過不足なく伝わっているか等を評価し合うことで、客観的な視点を養うことができます。
架空のプロジェクト課題に対して報連相を徹底するワーク
目的:報連相の実践力、主体性の強化
新製品の企画を進める・展示会の準備を行うなど、架空のプロジェクトをテーマに進行するなかで、報連相をいつ・どのように行うべきかを意識して取り組むワークです。
途中で上司役から追加指示やトラブル発生のアナウンスが入る仕掛けを入れることで、状況変化に応じた報連相の重要性を体感できます。終了後は、報連相のタイミングや内容について振り返りを行い、適切な報連相とは何かを学びます。
このように、ビジネス型のグループワークは、新入社員が実務で必要となる基礎スキルを、体験的に学ぶことができる点が最大の特徴です。配属前に、働くイメージを具体化させ、即戦力としての意識を高めるためにも非常に有効な研修手法と言えます。
作業型のグループワークのネタ
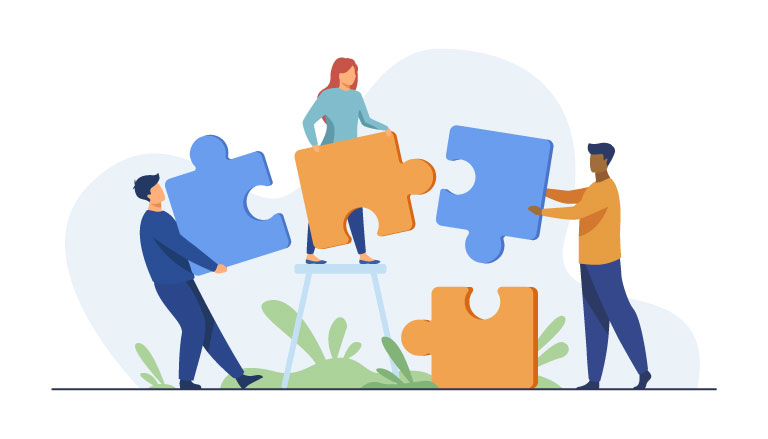
作業型のグループワークは、課題解決やモノづくりを通じて、チームで協力しながら成果物を完成させる形式です。資料作成やポスター制作など、手を動かして取り組むことで、役割分担力、協働力、計画性が自然と身につきます。
この形式は、発言の多さが評価されるディスカッション型とは異なり、作業を通じて貢献することが評価されるため、話すのが得意でない新入社員でも参加しやすいのが特徴です。
成果物が目に見える形で残るため、振り返りやフィードバックの材料にもなりやすく、PDCAの基本サイクル(計画・実行・確認・改善)を体験的に学ぶことができます。
では、代表的な作業型グループワークのネタを5つご紹介します。
組み立て紙飛行機実習
目的:コスト意識、計画力、チームワークの強化
仕様書・評価基準に沿って、グループで紙飛行機を作り、飛距離とコストのバランスで評価される実習です。遠くに飛ばすことだけを追求するとコスト超過になるため、品質・コスト・納期の意識を持ちながらチームで最適解を目指します。
製造業だけでなく、業務全般に通じる、計画的に進める力や資源を無駄にしない意識を育むことができます。
自社のチラシやイメージキャラクターの作成
目的:発想力、企業理解、協働力の向上
自社の商品・サービスを題材に、オリジナルのチラシやイメージキャラクターを作成するワークです。限られた時間内で、どの情報を載せるか、どのように魅力を伝えるかをチームで話し合い、形にしていきます。
クリエイティブな要素が求められるため、楽しみながら企業理解を深めることができ、発表を通じてプレゼンテーション力も鍛えられます。
ペーパータワー
目的:計画性、役割分担力、改善力の養成
限られた枚数の紙を使い、できるだけ高い塔を作るシンプルなワークです。事前に計画を立てずに作り始めると、安定性に欠けたり、資材が足りなくなったりするため、事前の戦略立案と役割分担が重要になります。
時間内に複数回チャレンジできる形式にすることで、トライ&エラーを繰り返しながら、改善する姿勢を体験的に学ぶことができます。
マシュマロチャレンジ
目的:創造力、試行錯誤力、柔軟な発想の習得
パスタ、テープ、ひも、マシュマロを使って、制限時間内にできるだけ高いタワーを作るワークです。最上部にマシュマロを乗せるというルールがあり、構造のバランスや柔軟な発想が求められます。
失敗を恐れずに試行錯誤することで、計画と実行のバランス感覚や、チーム内で意見を出し合う重要性を実感できます。アイスブレークとしても人気のワークです。
制限時間内に「業務マニュアル」を作成するワーク
目的:情報整理力、伝達力、チームでの効率的な作業力
架空の業務(例:来客対応、会議準備など)をテーマに、新入社員でも理解できる業務マニュアルをチームで作成するワークです。限られた時間内で、「何を、どこまで、どう伝えるか」を整理し、わかりやすい形にまとめる力が試されます。
単なる作業にとどまらず、読み手の立場に立つ力や、業務プロセスを論理的に整理する力が養われるため、実務に直結するスキル習得につながります。完成したマニュアルは、他チームと交換して評価し合うことで、さらなる改善点も発見できます。
このように作業型のグループワークは、楽しみながらチームで成果を出す経験を積める点が大きな魅力です。達成感を味わうことで自信にもつながり、今後の業務に向けた前向きな姿勢を引き出す効果が期待できます。
ゲーム型のグループワークのネタ

ゲーム型のグループワークは、ルールに基づいた遊びやシミュレーションを通じて、楽しみながらチームワーク、発想力、コミュニケーション力を養う形式です。熱中して取り組みながら、協力する難しさや情報共有の大切さを自然に体感できる設計がポイントです。
特に新入社員研修では、緊張を和らげたり、同期同士の交流を深めたりする効果も期待できます。一方で、目的や振り返りをしっかり設計しないと、単なるレクリエーションで終わってしまうリスクもあるため、「なぜこのゲームを行うのか」を明確に伝え、終了後に学びを言語化することが重要です。
では、研修に適したゲーム型グループワークのネタを5つご紹介します。
協力ゲーム
目的:非言語コミュニケーション力、チームワークの強化
チームメンバーそれぞれに異なる形の図形(例:三角形、四角形、平行四辺形など)が配布され、言葉を使わずに図形を交換し合い、全員が同じ形を完成させるゲームです。
制限された状況下で、いかに相手の意図をくみ取り、協力し合うかが求められます。言葉に頼らないコミュニケーションの難しさを体感でき、チームで目標達成するための工夫が促されます。
伝言ゲームを活用した報連相ワーク
目的:正確な情報伝達力、報連相の重要性理解
一般的な伝言ゲームをビジネスシーンに応用し、業務連絡風のメッセージを口頭で伝えていきます。最後の人が内容を発表した際に、どこで情報がずれたのかを確認することで、情報の正確な伝達の難しさと、報連相における確認の重要性を学びます。
ミスが起こることを前提に、どう防ぐかを振り返ることで、実務に生かせる学びを深めます。
ビジネスシミュレーションゲーム
目的:意思決定力、経営視点、チーム戦略の体験
架空の会社を経営するシミュレーションゲームです。チームごとに「どの商品に投資するか」「コストをどう抑えるか」「リスクにどう対応するか」など、複数の選択肢から意思決定を重ね、一定期間後の成果(利益や市場シェア)を競います。
経営的な視点や、チーム内で戦略を立てる力が求められ、単なるゲームでは終わらない深い学びが得られます。意思決定の難しさや、情報共有の重要性も実感できるワークです。
宝探しコミュニケーションゲーム
目的:情報整理力、役割分担、効率的なコミュニケーションの習得
チーム内で限られた情報カードを持ち寄り、協力して宝の場所を推理するゲームです。全員が持つ情報は一部しかなく、適切なタイミングで情報を共有することが成功の鍵となります。
このワークを通じて、必要な情報をいかに集約し、無駄なく伝えるか、また、チームでの役割分担やリーダーシップの重要性も体験的に学ぶことができます。
サウスポールゲーム(飛行機遭難ゲーム)
目的:合意形成力、論理的思考、リーダーシップの育成
「飛行機が南極に不時着し、限られた物資の中から生き延びるために優先順位を決める」というシナリオで進行する有名なグループワークです。個人で順位を決めた後、チームで話し合って最適な順位を導き出す過程で、論理的な説明力や、他者の意見を尊重しながら結論を出す力が問われます。
ビジネスにおける合意形成の難しさと重要性を実感でき、リーダーシップやフォロワーシップを発揮する良い訓練になります。
このように、ゲーム型のグループワークは、楽しさを生かしながら、チームで成果を出すために必要な力を自然に引き出すことができます。しっかりと目的を伝え、振り返りを行うことで、新入社員にとって実務に直結する、学びの多い時間となります。
コンサルタント厳選!学びが多い特におすすめのグループワークネタ5選
これまでご紹介した20個のグループワークの中から、特に新入社員研修で効果を発揮しやすい5つのネタを厳選しました。
これらのワークは、楽しみながらも新入社員に必要な「主体性」「チームワーク」「ビジネスマナー」「課題解決力」など、実務に直結する力をバランスよく養える点が特徴です。
特におすすめのグループワーク5選
会社案内の作成(プレゼンテーション型)
おすすめポイント:自社の理念やビジョン、歴史、価値観、組織構造、事業内容、強みなどを調査・整理することで、会社理解を深めることができます。配属後は業務に追われてしまうため、事前にプレゼンテーションスキルとあわせて会社への理解を深められる点が大きなメリットです。
来客対応ロールプレーイング(ビジネス型)
おすすめポイント:新入社員研修で学んだビジネスマナーを、実践的に身につける場となります。座学だけでは定着が難しい内容も、繰り返し体験することで即戦力として活かせます。チーム内で役割を分担し相互フィードバックを行うことで、習得意欲も高まりやすくなります。
紙飛行機実習(作業型)
おすすめポイント:仕様書や評価基準に基づいて、品質・コスト・納期を意識しながら最適解を目指します。製造業では特に、配属前に業務の考え方を体験的に学べる貴重な機会となります。ビジネスにおける「結果がすべて」という厳しさも体感でき、顧客志向を育むことができます。
協力ゲーム(ゲーム型)
おすすめポイント:相手の意図を感じ取り、自分の意図を伝えるというコミュニケーションの本質を体感できます。言葉なしに相手に伝える経験を通じて、コミュニケーションには表情・身振り・手ぶりも重要なサインになることが理解でき、人と一緒に働いていく上で役立つ表現力や配慮力を高められます。また、制約のある状況でもチームで協力しながら成果を出す力が養われます。
サウスポールゲーム (ゲーム型)
おすすめポイント:多様な意見をまとめ、合意形成していくプロセスを体験できます。ビジネスにおいては関係者の納得を得ながら進める力が求められるため、その第一歩として非常に有効です。限られた時間の中でリーダーシップやフォロワーシップを発揮し、自分の役割を考えて行動する力も鍛えられます。
これら5つのグループワークは、いずれも弊社の研修プログラム内で実施可能です。各ワークには適切なファシリテーションや振り返りの支援が組み込まれており、新入社員の実践力を高める設計となっています。組み合わせて導入することもできるため、詳細が気になる方はぜひ以下よりお問い合わせください。
最後に
グループワークは、ただ実施するだけでは十分な効果は得られません。重要なのは、研修の目的に合ったワークを選定して、適切に進行し、振り返りを行うことです。
今回は、20個のネタをご紹介しました。その中でも、厳選した5つのワークは、新入社員の主体性やチーム力を引き出すうえで非常に有効です。
「自社でうまく実施できるか不安」「もっと効果的にグループワークを活用したい」とお感じの際は、ぜひ弊社までご相談ください。目的に応じたワークの選定から、ファシリテーション、振り返りの実施まで、一貫してサポートいたします。
新入社員の成長を加速させる研修の構築に、ぜひご活用ください。